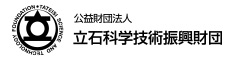[研究助成(A)(B)] 40件
Study of group rod migration system using nonlinear synchronization
― Learning from the migration method of sea urchins ―
田原 淳一郎
東京海洋大学 学術研究院海洋電子機械工学部門 教授
非線形同期を用いて,ウニを模したロボットを制御する手法の研究を実施した。非線形振動子の van derPol方程式を拡張し,多角形におけるロッド運動の制御を実施した。Python と MATLAB を活用した非線形同期システムを構築した。本アルゴリズムをマイクロコンピュータに実装し,デルタ型に接続したエアシリンダを用いて任意の同期モードに制御出来る事を確認できた。
Development of Information Presentation Technology to Control Mindsets for Breaking Through the Limitation and Behavior Change
双見 京介
立命館大学 情報理工学部情報理工学科 助教
本研究では,人のマインドセットのサポータとなるコンピュータ技術の実現を目指し,マインドセットの向上や変容を簡便に行う情報提示技術の開発を目指した。情報提示システムの利用が起こす無意識の現象を制御することで,行動変容のための競争情報提示手法と,疲労制御のための自己情報フィードバック手法を開発し,本研究構想の実現可能性を確認した。
Experimental attempt of cryopreservation for uncryopreservable bioresources by inkjet printing based superflash freezing
秋山 佳丈
信州大学 学術研究院繊維学系 教授
これまでに,超瞬間的に凍結することで凍結保護剤を用いない細胞の凍結保存が可能であることが確認できていたが,本研究では解凍工程に着目し,その生存率と再現性の向上を目指した。特に,自動解凍装置や衝撃離脱法を開発することで,従来法と同等の生存率を得ることができた。現在,各種バイオリソースへの本手法の適用に向けて研究を進めている。
Physiological Evaluation of Neural Basis behind Proficiency of Prosthetic Walk
牛山 潤一
慶應義塾大学 環境情報学部 准教授
本研究では健常者ならびに利用歴の異なる股義足ユーザーを対象に,健常側・義足側の双方から表面筋電図を取得し,筋シナジー解析を用いて習熟度による義足歩行制御戦略の差異を検討した。結果,義足歩行の習熟の背景には,既存の筋シナジーの活動タイミングの変調や筋シナジー自体の再編といった,構造面・機能面双方の可視的変化が寄与している可能性が明らかとなった。
Development of a visual training system to expand the visual function domain of the elderly
木下 史也
富山県立大学 工学部情報システム工学科 講師
本研究課題では,MCI の早期発見を目的として利用者の奥行き知覚能力を定量的に評価することができる VRコンテンツの開発を行った。コンテンツは Unity を用いて開発し,視線計測機能の付いた HMD から提示することによって視線情報を取得する。その結果,利用者の瞳孔間距離を特徴量とすることで,奥行き知覚能力を定量評価することが可能であった。
Identifying joint coordination related to skill for the development of skill transfer systems
木村 新
国立スポーツ科学センター 研究員
本研究では,投動作を対象に関節間の協調関係を分析するための方法論を構築し,実験的検証を行った。既存の研究は関節間が協調していたという結論に留まっていたものの,本研究で提案した方法論により特定の関節間の協調関係について検討することが可能となった。このような具体性の高い情報は,運動技能の継承を考える上で有益である。
Combination of LED lights to improve the color discrimination for people with color blindness
茂里 康
和歌山県立医科大学 医学部 教授
男性の 6〜8% が該当する先天性色覚障がい者の間違いやすい色の識別能力を高めるための光源の基礎を確立した。すなわち,必須となる光の波長を見出し,演色性が異なる光スペクトルを 2 種類定義し,その有効性を色覚障がい者による被験実験,あるいは,シミュレーションによって調べた。Ⅱ型色覚者用の光源に比べ,Ⅰ 型色覚者用の光源は演色性が悪かった。
Search for optimal photoplethysmographic measurement conditions for high- precision cuffless blood pressure estimation
任田 崇吾
石川工業高等専門学校 電子情報工学科 講師
高血圧は心血管疾患の危険因子として,世界的な問題となっており,日常的な血圧計測が大切となる。本研究では,光電脈波単独でのカフレス血圧推定法の開発を目指し,センサ間距離が光電脈波に与える影響および,光源波長が血圧推定法に与える影響を検討した。その結果,血圧の種類により,精度の高い光源波長が異なることを明らかにした。
Development of Distributed Tactile Sensor Soft- MPS Array
長濱 峻介
京都先端科学大学 ナガモリアクチュエータ研究所 助教
本研究では,磁気拘束した金属粉体をソフトマテリアルで固定化することで得られる柔軟な抵抗式触覚センサSoft-Magnetic Powdery Sensor(Soft-MPS)をアレイ化することで,多点センシングが可能なデバイスの開発を目指した。センサアレイとその信号処理用の回路の製作,および安定的なデータを取得するために基板にSoft-MPS を接合する手法の評価を行った。
Development of Robotic Technology to Experimentally Induce “Feeling of a Presence” by Cooperative Actions
原 正之
埼玉大学 大学院理工学研究科 准教授
本研究では,多自由度パラレルリンクロボットの設計・開発を行い,協調的動作を用いた FoP 研究への適用可能性について検討した。また,開発したロボットを基礎として健常者を対象とした FoP 実験も実施し,手を刺激対象としてもFoP を実験的に誘起できることと,刺激される手の位置によって FoP の出現位置を変化させることができる可能性を示唆した。
Perception of pseudo- haptics in virtual reality
福井 隆雄
東京都立大学 システムデザイン学部 准教授
バーチャルリアリティ環境下において,手腕モデルと接近物体の衝突時に生じる擬似触覚の生起強度について検討し,接近物体の衝突時の減速率が大きいほど,そして,手と物体の接触イベントを視覚的に提示することにより,主観的評価値が大きくなることが示された。さらに,物理的な触覚刺激をともなわない擬似触覚経験による掌表面温度の上昇も認められた。
Deep Learning- based Framework for 3D Character Design from Rough Sketch
福里 司
東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教
ラフなスケッチ画を用いて高品質な 3DCG キャラクタアニメーション制作を実現するために,ユーザが描くスケッチ画自体の品質を向上させる技術とスケッチによるキャラクタモーションの制御技術を考案する。
Invention of a wearable EEG system for clinical use in super- aged society
松本 理器
神戸大学 大学院医学研究科 教授
本研究では,神戸大学医学部附属病院のてんかん外来および認知症センターを受診し,病歴聴取上てんかんが疑われた患者のうち,入院して長時間ビデオ脳波検査 (VEEG) を実施された患者を対象として,ウェアラブル脳波デバイスを用いた終夜脳波記録を行い,てんかん性放電の検出に有用な電極部位の同定と装着方法の至適化を図っている。
Development of Skill Transfer Support System for Uta- sanshin based on Harmony between Human and AI
宮城 桂
沖縄工業高等専門学校 情報通信システム工学科 講師
重要無形文化財「組踊歌三線」において,琉球音階の独特な音響的特徴に関する記載は無く,熟練者の技能は目下口伝のみによって伝承される。一方,昨今では様々な学術分野における科学技術の統合化が進められており,これによる新たな価値の創出が求められている。本研究課題では,歌三線と工学の融合による技能伝承支援基盤の確立を目指す。
Protocol Generation from Life Science Experiment Videos
森 信介
京都大学 学術情報メディアセンター 教授
生命科学実験を対象に,その実施映像から手順文 (プロトコル) を自動的に生成すること及び言語による動画検索システムの実現を目指して研究を行い,32 回の生命科学実験動画を収録,データセットとして公開した。ついで実験動画とプロトコルの自動対応を実現し,プロトコル中の各手順の言語クエリに対してその実施区間を検索表示することを可能とした。
Communication training for individuals with autism spectrum disorder through robot cooperative tasks
渡辺 哲陽
金沢大学 理工研究域フロンティア工学系 教授
本研究では,自閉スペクトラム症 (Autism Spectrum Disorder: ASD)者の協調性を向上させる手法を検討した。ロボットを二人一組で操作するような訓練を,難易度を上げながら合計8回実施することで,ASD 者の協調性が向上するかを調査した。その結果,訓練の相手に対する協調性の向上が認められた。ただし,訓練相手以外の方に対する協調性は必ずしも向上するとは言えなかった。
Development of the gait assessment devise and gait stability index using inertial measurement unit
秋山 靖博
名古屋大学 大学院工学研究科 助教
小型慣性計測ユニットを装着して歩行中の加速度波形を計測した。波形を既存の歩容評価指標と関連付ける統計処理を行い,慣性ユニットを用いた歩容評価の妥当性を検証した。急な加減速を含む多様な歩容において,加速度波形から安定性指標を推定する数値モデルを構築した。
Development of free- space optical communication system using two- dimensional patterns
池田 佳奈美
大阪公立大学 大学院工学研究科 助教
光無線通信システムは自由空間中を伝搬する光によって情報伝達を行う通信システムである。ソフトウェアによる暗号化と併用可能な,ハードウェア内の光学系構成による光無線通信の安全性向上を目指し,2 次元空間変調による暗号化を導入した光無線通信システムを構築した。
Effects of Nonverbal Information and Perspectives of Virtual Avatars on Self- Disclosure
市野 順子
東京都市大学 メディア情報学部 教授
人間関係や絆を築く上での自己開示の重要性と,遠隔コミュニケーションツールへ拡充への期待を踏まえ,本研究 (テーマ 1)では,①ビデオ会議,②バーチャルアバターと自己の外見的類似性のあるアバター。③類似性のないアバターを比較する実験を行った。その結果,類似性のないアバター,類似性があるアバター,ビデオ会議の順で参加者の自己開示が促された。
Developing machine- learning models for estimating the meanings and functions of nonverbal behaviors in convrsations
大塚 和弘
横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授
人の対話における非言語行動の機能を認識・理解するため『非言語機能スペクトラム』という新概念を提唱し,その計算基盤の構築を行った。特に対話者の頭部運動が担う複数の機能に着目し,それらを頭部姿勢角の時系列データなどから認識する深層学習モデルを構築し,また,認識された頭部運動の機能から対話者の主観的印象を予測するモデルなどを提案した。
Developing a system for acquiring work information for human- machine cooperation in a large- scale rice field
大山 克己
大阪公立大学 大学院現代システム科学研究科 教授
大規模水田における労働生産性を向上させるためには,人間と様々な機械 (トラクタ,コンバインなど)とが協調して,作業を計画通りに完了する必要がある。そこで本研究では,大規模水田における人間-機械協調を促進することを目的として,作業情報 (位置や進捗状況)を遠隔でリアルタイムに取得するための安価なシステムを開発した。
Biofeedback system for sensory substitution of muscle coordination and application to gait learning
木伏 紅緒
神戸大学 大学院人間発達環境学研究科 助教
筋活動バイオフィードバックによって,歩行中の身体重心加速度が安定するかを検証した。実験条件は,ヒラメ筋,前脛骨筋,半腱様筋のフィードバック条件とフィードバックなし条件の 4 条件を設定し,身体重心加速度の二乗平均平方根を比較した。筋活動バイオフィードバックによって,前後方向と鉛直方向の身体重心加速度が安定することが明らかとなった。
Development of two dimensional imaging system with diamond NV and fiber array
桑波田 晃弘
東北大学 大学院工学研究科 准教授
高精度ながん診断のために,ダイヤモンド窒素空孔センタと光ファイバアレイを用いた 2 次元イメージング技術を開発した。微細な磁場構造の観測において,2 次元での磁場ベクトルイメージングに成功した。今後は,生体応用に向けての高感度化やシステムの最適化を実施し,医療現場で使用可能な機器を開発し,がん患者の生活の質の向上に貢献することを目指す。
Predicting the effects of noninvasive brain stimulation methods on improving motor function based on individual brain structure
小島 翔
新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科 講師
経頭蓋直流電流刺激は非侵襲的に脳を刺激する手法のひとつであり,一定時間の刺激によって脳卒中患者の運動機能等を向上させることができる。一方で,その刺激効果はバラつくことが報告されている。そこで,我々は,脳情報解析技術を用いて個人の脳構造特性から介入効果のバラつきを是正することを目的に研究を実施した。
Facilitation technique of central fatigue recovery
齋藤 輝
九州産業大学 健康・スポーツ科学センター 助教
本研究の目的は,経頭蓋直流刺激による中枢神経回路の変調が疲労回復に与える影響を明らかにすることであった。10 分間の経頭蓋直流刺激を与えた後に,第一背側骨間筋を疲労困憊まで随意収縮させた。そして,中枢神経回路の興奮レベルを計測し,中枢神経回路の疲労回復に至るまでを観察した。経頭蓋直流刺激によって中枢神経回路の疲労回復が促進することはなかった。
Human- machine collaboration based on the integration of data- driven driving intelligence and haptic shared control
齊藤 裕一
筑波大学 システム情報系 助教
本研究課題は,危険予測知識のデータに基づく危険度推定を運転支援スキームに組み込むことに着目し,経験知識/データベース/機械学習(AI) という情報学と,触覚的シェアードコントロールという知能機械工学の融合的アプローチに基づき「運転知能の高度化」ならびに「人と機械の協調」の進展を図るものである。
Development of neurofeedback- based attention training system considering individual differences in the human brain
櫻田 武
成蹊大学 理工学部理工学科 准教授
ニューロフィードバックと呼ばれる,計測した脳活動を本人にリアルタイムで提示する手法を用い,ヒトの注意機能向上を目的とした訓練システムを開発した。構築したシステムを用いた数日間の訓練の結果,個々の低次感覚野における応答増幅に成功した。さらに,その脳活動変化に伴って,注意機能向上を示す行動変容も確認された。
Research on a Guide Dog Robot of Expressing Visual Environemnt by Voice
張 斌
神奈川大学 工学部機械工学科 助教
本研究で開発した盲導犬ロボットは道誘導機能を実現する際,ユーザの社会性のニーズを考慮し,ロボットに搭載したセンサを用いて,ユーザ周囲の視覚環境をセンシングし,途中の風景や街中のシーンを理解し,音声で表現する。視覚障碍者が街中を散策し,周囲の環境や街中のシーンを楽しめることを目指す。盲導犬ロボットの社会受容性を向上することが期待できる。
A nursing care robot that listens in consideration of the privacy of the elderly
瀬島 吉裕
関西大学 総合情報学部 准教授
本研究では,お節介を行うための「①高齢者の状態推定技術」と,プライバシーに配慮した「②お節介な発話支援技術」を主要技術として位置付け,居住空間内の温度センサから人の状態を推定するアルゴリズムと,利用者の音声から傾聴感の高い瞳孔のミラーリング表現技術によって,お節介による発話支援の有効性を示した。
Development of improvement for scan technique of X- ray with deep laerning
髙島 弘幸
札幌医科大学 附属病院放射線部 副部長
CT 画像を用いて膝関節の単純X線像を模擬した画像を作成し,deep learning を用いて適切なポジショニング画像となる画像の角度を求めるプログラム開発を目的とした。今回の検討では,学習時のaccuracyは0.94と高い値が得られていたのに対してテスト画像の分類では accuracyは0.81 と低い値になった。
Development of glass nanofilter based power generator using energy from human behavior
田中 陽
国立研究開発法人理化学研究所 生命機能科学研究センター 集積バイオデバイス研究チーム チームリーダー
本研究では,水とガラス微細流路の電気相互作用を利用し,圧力により水が流れる限り発電が持続する,人の動きに適した新環境発電機を創成した。これにより,人は自然な動作で機械を使えて機械は電源を安定確保できメンテナンス不要,という人と機械が完全融和した社会を実現できる。
Sensor- integrated MEMS Reservoir Computing using Ring Resonator
土屋 智由
京都大学 大学院工学研究科 教授
機械学習機能を一体化した知能化センサ実現のため,非線形振動子群で構成する物理リザバーとセンサとなる機械構造を Si 基板上に一体製作する MEMS リザバーコンピューティングを提案し,円環型振動ジャイロスコープに適用するための検討を行った。サーバへの通信量,消費電力を低減した高機能高信頼 IoT インフラを提供,より安全で安心な社会の構築に寄与する。
Effects of calibrated and various white noises on improving postural fluctuations
常盤 達司
広島市立大学 大学院情報科学研究科 准教授
立位姿勢に対する制御機能の低下は,例えば「めまい」や「ふらつき」などの平行機能障害を引き起こし,特に高齢者に顕著である。本研究では,音刺激が立位姿勢制御向上に及ぼす効果を調査するために,ダミーヘッドを用いて音圧や周波数を事前に校正した種々のホワイトノイズが立位姿勢制御に及ぼす効果を評価した。
Development of a hybrid rehabilitation support system to improve the balance ability of elderly people
中野 英樹
京都橘大学 健康科学部理学療法学科 准教授
本研究では,脳活動を効果的に修飾させるニューロフィードバック装置と脳内運動イメージトレーニングを併用したハイブリッド型リハビリ支援システムを開発した。当該システムを用いたトレーニングは,健常者の立位姿勢制御能力を向上させることを明らかにした。本研究は,高齢者のバランス能力の改善と転倒リスクの軽減に貢献する可能性を示唆した。
Development of a biofeedback system in which EMG, FES, and tactile presentation are interactively harmonized in virtual / augmented reality
松居 和寛
大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教
本研究は,電気刺激を用いて取得できる神経筋骨格系モデルを用いて,筋電図,機能的電気刺激触覚を用いたバイオフィードバックを,仮想/拡張現実をプラットフォームとしてインタラクティブに結合したシステムを開発するものである。
Development of a Transtibial Prosthesis for Puttering Cycling
村木 里志
九州大学 大学院芸術工学研究院 教授
下腿切断者がサイクリング (自転車のペダリング)を楽しむための義足,自転車のペダル,それらをつなぐアタッチメントを開発することを目指し,ペダリングにおいて足関節の運動 (底屈および背屈)が働かないことによる問題点およびペダルと接続する足底部の位置(つま先側,中央)を検討した。
Motion Cotnrol for Advanced Human Motion Reproduction
元井 直樹
神戸大学 大学院海事科学研究科 准教授
モーションコピーシステムは人間動作における位置・力情報を抽出・保存する動作再現フェーズと,保存データに基づき動作再現を行う動作再現フェーズから構成される。本研究では,動作再現フェーズにおいて反復学習制御を用いることで,再生速度を高速化し,再現動作の高度化を目指した。また,実機実験により提案手法の有効性を検証した。
Integrated Artifial Odor Sensor Electronics
柳田 剛
東京大学 大学院工学系研究科 教授
本研究では,物理センサと比較してその科学技術が大きく立ち遅れている“嗅覚センサ”に着目し,申請者が独自に展開してきた ①堅牢な分子識別機能を有する金属酸化物ナノワイヤ界面と ②分子捕集部とセンサ部が集積化された分子センサ構造により“堅牢な集積化人工嗅覚センサ”を実現する。
Development of a soft robot hand- arm system towards human- robot collaboration
山川 雄司
東京大学 大学院情報学環 准教授
本研究は,人との協調作業を可能とするソフトロボットハンドシステムの開発を目指している。その実現のため,伸長可能かつ剛性可変な構造を有し,運動制御や物体把持が可能なプロトタイプシステムを構築するとともに,高速画像処理を駆使し,ロボットの先端位置の高速視覚制御を達成した。実際に構築システムを用いて,運動制御および物体把持を実現した。
CYBERNETIC ELECTRICAL STIMULATOR DEVELOPMENT FOR CHRONIC UPPER- EXTREMITY HEMIPARESIS TREATMENT
南 征吾
群馬パース大学 大学院保健科学研究科 教授
本研究の環境にしたがって生活適応力を引き出す装置は,対象物 (環境)と身体反応の関係性を捉え人の予測制御を促し,生活適応力を高められるものある。この装置の開発は,神経系機能の情報と機械の自動制御を統合し,人と機械の相互関係を促進する。本研究では,身体反応と外部環境を取り込み,人の動きを促通する研究機器の開発に取り組んだ。