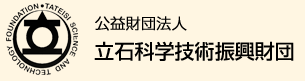2024.04.24
橋本光博
2024年度助成金贈呈対象決定のお知らせ
2024年度の助成対象が、選考委員会による厳正な審査と理事会の承認を経て決定しましたのでお知らせいたします。本年度は、研究に対する助成として54テーマ、前期国際交流(後期は9月下旬決定)に対する助成として13テーマを選定・決定いたしました。助成対象(助成者と助成課題)については、以下をご参照ください。また、助成対象を代表して、2024年度研究助成(S)の概要を抄録として抜粋しています。贈呈式は、5月17日(金)にオムロン株式会社 みやこホールにて行います。贈呈式の参加は、研究プログラム別代表者と財団関係者とし、助成金受領者はウェビナーにて参加します。 研究助成(S) 研究助成(A) 研究助成(B) 研究助成(C) 国際交流助成 おもな研究助成の抄録 ■今回および累積の助成金額 研究助成件数・額 国際交流助成件数・額 合計件数・額 今回(2024年度) 54件1億5,764万円 (前期のみ) 13件(前期のみ) 761万円 67件1億6,524万円 累積(1990年度~2024年度) (立石賞21件を除く) 1,038件29億5,773円 604件3億1,298万円 1,642件32億7,071万円 今回助成される皆様には是非とも研究課題を達成していただき、最先端の科学技術でグローバル社会に貢献していただくこと、そしてさらにはこれらの中から、将来の立石賞受賞者が輩出されることを期待します。 2024年度 研究助成 受領者および研究課題一覧 【研究助成(S)】 最大3,000万円(間接経費含む)/3年を助成 研究期間:2024年4月~2027年3月 No. 代表者氏名 所属・職名 研究課題 1 馬場 俊彦 横浜国立大学 工学研究院/先端科学高等研究院 教授 人とロボットの共生を可能にする光集積型4D LiDARセンサ 申請件数:18件、採択件数:1件 Topへ 【研究助成(A)】 最大250万円(直接経費)を助成 研究期間:2024年4月~2025年3月 No. 氏名 所属・職名 研究課題 1 李 信英 山梨大学 大学院総合研究部工学域 助教 触診技術伝承を目指した耳小骨可動性計測訓練シミュレータの開発 2 石井 佑弥 京都工芸繊維大学 繊維学系 准教授 無給電状態で静的および動的な圧力センシングが可能な編み手袋の開発 3 石原 尚 大阪大学 大学院工学研究科 講師 高度な表現力を備えるアンドロイドの感性評価に基づく対人印象制御法の開発 4 市川 健太 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 助教 咬合力エナジーハーベスティングによるバッテリーレスマウスガード型デバイスの開発 5 猪俣 武範 順天堂大学 医学部眼科学講座 准助教 VRを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器の社会実装に向けた橋渡し研究 6 大西 鮎美 神戸大学 大学院工学研究科 助教 柔軟触覚センサによって浮腫の状態を計測するウェアラブルデバイスの開発 7 大道 英二 神戸大学 大学院理学研究科 准教授 オンチップテラヘルツ分光システムを用いたラベルフリーバイオセンシング 8 奥田 裕之 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授 人間と機械の相互影響度の計量にもとづく他者への配慮の実現 9 尾崎 公美 浜松医科大学 放射線診断学講座 准教授 未病検知を目指した画像診断機器による臓器の生理機能評価及び加齢性機能低下の検証 10 加藤 貴英 豊田工業高等専門学校 一般学科 准教授 実現場での階段昇降動作データに基づいた転倒を検知するための機械学習的アプローチ 11 川上 玲 東京工業大学 工学院システム制御系 准教授 基盤モデルに基づく手話対話システムの構築 12 北村 知也 東京理科大学 創域理工学部電気電子情報工学科 助教 EMSを用いた位置制御・力制御の統合アプローチと制御性能の評価 13 桐本 光 広島大学 大学院医系科学研究科 教授 AIロボットと迷走神経刺激によるデュアル・クローズドループ型手指機能訓練法の開発 14 金 太一 東京大学 大学院医学系研究科医用情報工学 特任准教授 人間機械協調型複合現実融合技術を用いた手術支援基盤技術の開発 15 小西 克巳 法政大学 情報科学部 教授 災害現場での救援活動を支援する超小型3次元再構成センサの開発 16 斎藤 寛樹 東京工科大学 医療保健学部リハビリテーション学科 助教 経皮的脊髄刺激による下肢筋協調パターンの変調:動作向上のニューロモジュレーション 17 助川 信太郎 香川大学 医学部歯科口腔外科学講座 准教授 病理医が信頼を寄せる人協調型AI診断システムの開発 18 中後 大輔 関西学院大学 工学部知能・機械工学課程 教授 筋シナジーを用いた随意運動誘引手法による自発的動作に寄り添う正常歩行訓練装置 19 林部 充宏 東北大学 工学研究科 教授 Mixed Realityと慣性センサを用いた空間認知と運動機能の定量化システム 20 平 理一郎 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 准教授 全身体BMI 21 平井 宏明 大阪大学 大学院基礎工学研究科 准教授 動的プリミティブの運動制御仮説に基づく歩行・走行への介入と訓練効果 22 福田 篤久 九州大学病院 小児外科 助教 AI自動評価技術を用いた内視鏡手術技術の定量化と次世代教育システムの開発 23 藤井 綺香 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究員 複合現実空間における漫符を活用したロボットによる自己表現生成AIに関する研究 24 部矢 明 名古屋大学 工学研究科 准教授 MRI・CT画像下治療のための多自由度空圧ステッピングモータの開発 25 堀井 辰衛 東京工業大学 工生命理工学院 研究員 高分子ゲル超薄膜を用いた指先に貼付可能な全貼付型触覚センサの開発 26 増田 寛之 富山県立大学 情報工学部知能ロボット工学科 教授 学習者の主体的な行動を促すグループワーク支援ロボットの研究 27 松井 勇佑 東京大学 情報理工学系研究科 講師 Advanced Vector DB:データ構造ドリブンなLLM知識注入 28 宮田 紘平 東京大学 大学院総合文化研究科 助教 サイバー空間におけるラポール形成へ向けたシステム開発 29 森 健太郎 舞鶴工業高等専門学校 電気情報工学科 講師 身体的特徴のデータ解析による定量的技術評価・向上システムの開発 30 山田 泰之 法政大学 デザイン工学部システムデザイン学科 准教授 光弾性を利用した力覚変色表示ソフトアクチュエータの研究開発 31 山本 真人 関西大学 システム理工学部物理・応用物理学科 准教授 超低消費電力リアルタイム学習を可能にする二次元半導体光電子メモリの開発 32 横山 光 東京農工大学 大学院工学研究院 准教授 微小針電極による超高密度脳波計測:脊髄損傷者の手指動作を脳波から高精度に解読する 33 葭田 貴子 東京工業大学 工学院機械系 准教授 ロボットアーム錯覚は可能か 34 吉村 優子 金沢大学 人間社会研究域 教授 RLHFを用いた自閉症児の個性に合わせたLLMの最適化と寄り添う対話ロボットへの実装 35 若山 清香 山梨大学 発生工学研究センター 助教 AIを用いた顕微授精アシストシステムの開発 申請件数:191件、採択件数:35件 Topへ 【研究助成(B)】 最大500万円(直接経費)を助成 研究期間:2024年4月~2026年3月 No. 氏名 所属・職名 研究課題 1 鵜木 祐史 北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授 骨導デバイスを利用した聴覚拡張現実の実現 2 楊 期蘭 東京大学 大学院情報学環 助教 Investigating the Effect of AI on Meaningful Interpersonal Communication 申請件数:21件、採択件数:2件 Topへ 【研究助成(C)】 博士後期課程の学生に年間50万円(直接経費)を助成 研究期間:2024年4月~(最大3年間) No. 氏名 所属 研究課題 1 秋山 久遠 芝浦工業大学大学院理工学研究科 事故が起きる未来を変えるマイクロモビリティのための多重未来マップ予測システム 2 秋吉 拓斗 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 高齢者向けの身体接触を伴うカウンセリングロボットの実現 3 阿部 優樹 北海道大学大学院情報科学院 視覚障がい者のためのオンライン音楽ライブ向け動画視聴インタフェースの研究 4 安藤 ゆうき 東京工科大学医療保健学部 末梢血管の伝達関数である時定数の同定とその臨床応用 5 五十嵐 俊治 東京大学大学院新領域創成科学研究科 高齢者の自然発話における特徴量を用いた認知機能推定手法の開発 6 石川 慶一 東京大学大学院総合文化研究科 身体拡張技術発展に向けた義足歩行獲得を早める非侵襲脳神経刺激法の確立 7 伊藤 実央 埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科 エレクトロニクス技術を駆使した脳卒中者へのリハビリテーション介入基盤の確立 8 桶川 大志 東京大学大学院総合文化研究科 努力知覚の変調による全力運動パフォーマンス向上法の開発 9 國吉 佑輔 電気通信大学大学院情報理工学研究科 脳の神経回路構造に則した予測マップの構築とその機械学習への応用 10 黒田 彗莉 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 実世界における直観に反した運動の予測と言語生成 11 XUE XIAOZHONG 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科 深層学習を用いたOCTにおける網膜下液のセグメンテーションと黄斑浮腫早期診断 12 田中 健太 大阪大学大学院工学研究科 人間機械系の能力向上に向けた情報改変器の普遍的設計論の構築 13 田渕 史 京都大学大学院工学研究科 iPS細胞を用いた糸球体MPSによる高血糖、脂質異常症、高血圧の相乗効果の評価 14 中田 匠哉 神戸大学大学院工学研究科 サービス動的個人適応に向けた対話型ユーザニーズ外化システムの研究開発 15 原田 裕生 同志社大学大学院理工学研究科 高MHz帯域の強力超音波を用いた小型光流体レンズの開発とマシンビジョンへの応用 16 吉本 昂希 京都大学 医生物学研究所大学院生命科学研究科 荷重制御した周期的圧縮刺激を印加可能な骨-癌共培養装置の開発 申請件数:36件、採択件数:16件 Topへ 2024年度前期 国際交流助成 受領者および助成内容一覧 【国際会議発表】 最大60万円(直接経費)を助成 実施期間:2024年4月~2024年9月 No. 氏名 所属 参加する国際会議 開催地 1 小田 和哉 摂南大学大学院理工学研究科 International Symposium on Flexible Automation (ISFA) シアトルアメリカ 2 北田 敦也 京都大学大学院工学研究科 3rd Microphysiological Systems World Summit (MPS World Summit 2024) シアトルアメリカ 3 木下 史也 富山県立大学工学部情報システム工学科 HCI INTERNATIONAL 2024 ワシントンD.C.アメリカ 4 徐 雨曾 千葉大学大学院融合理工学府 46th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society フロリダアメリカ 5 神野 莉衣奈 東京大学大学院総合文化研究科 International Workshop on Gallium Oxide and Related Materials (IWGO) 2024 ベルリンドイツ 6 住 拓磨 東北大学材料科学高等研究所 FENS Forum 2024 ウィーンオーストリア 7 竹内 雅樹 東京大学工学系研究科 46th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society フロリダアメリカ 8 西舘 嗣海 千葉大学大学院融合理工学府 BioEM 2024(医用生体電磁気学学会 年次大会) クレタ島ギリシャ 9 藤崎 貴也 島根大学材料エネルギー学部 2nd CEMDI Symposium モントリオールカナダ 10 松田 汐利 神戸大学大学院システム情報学研究科 Optica Imaging Congress トゥルーズフランス 11 宮 愛香 北海道大学北海道大学病院 糖尿病・内分泌内科 米国内分泌学会 (ENDO 2024) ボストンアメリカ 申請件数:20件,採択件数:11件 【短期在外研究】最大100万円(直接経費)を助成 実施期間:2024年4月~2024年9月 No. 氏名 所属 研究課題 在留地域 1 末満 堅人 長岡技術科学大学技術科学イノベーション専攻 運動学習補助に向けたロボット-人間の相互作用神経メカニズムの解明 イギリス 2 Surantha Nico 東京都市大学理工学部電気電子通信工学科 IoT ベースのヘルスケアシステムにおけるサイバーセキュリティの課題の緩和に関する研究 シドニーオーストラリア 申請件数:5件,採択件数:2件 国際交流助成の助成内容は、選考時点のものです。 Topへ おもな研究助成の抄録 研究助成(S) 代表者氏名 馬場 俊彦 所属・役職 横浜国立大学 工学研究院/先端科学高等研究院 教授 研究課題名 人とロボットの共生を可能にする光集積型4D LiDARセンサ 研究概要 LiDAR は物体とその動きを3次元的に可視化するイメージセンサであり、自動運転の話題と共に世界的に開発が活発化している。しかし、現在は光ビームスキャナがメカ式のため、大がかりで高価で不安定な装置である。申請者はメカを用いない独自の光集積型LiDAR を 2016 年に提案、特許取得し、2021年、その動作実証に成功した。光集積型 LiDAR を実用化できれば、小型、低コスト、安定化が一気に進む。そして自動運転だけでなく、様々なモビリティやロボットの自律的な運用、その安心・安全を強力に支援する。また人の認証・見守り、VR・AR の高度化、立体地図を含むビッグデータの 3 次元化など、応用範囲が飛躍的に拡がり、人間と機械の融和に大きく貢献する。 Topへ